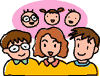今回の同行援護に関する学習会は,障害を持つ人が生活する上で困っている点をあげて,法整備なり,制度の改善を求めていこうという運営委員会での話し合いに端を発したものです。
それよりも前に,横浜の視覚障害のMさんからは同行援護に移行になると外出にかなりの制限がされるようになり,すでに同行援護に移行している事業所もあり,生活する上で困っている点という電話を受けました。9月15日に学習会をもつことになっているので,その事前学習ということで,同行援護を取り上げました。9月15日の残暑払いの日の午前中に,それぞれが抱えている問題点を話し合います。
問題点
Mさんより
これまで外出にはガイドヘルパーさんとボランティアさんをお願いしてきた。
1回の外出は6時間,6時間以上かかる外出だとお願いできない。同行援護に移行してから,例えばお稽古ごとについて言えば,お稽古をしている間待っていただくとその分の費用は自費になる。詩吟を習っているが,詩吟はお師匠さんがいるので,指導者がいる場合はその場にいていただくことができない。一人で座らなければならないと困ることが多い。ヘルパーさんに同行していただくと詩吟の2時間のお稽古の間一時間840円の費用が発生する。
病院への通院の場合でも診察室に入るとヘルパーさんが時間を計っていて,15分を過ぎると30分自己負担が生じる。自己負担分は生活保護を受けている人も同様なので外出を控えるようになると思う。
行った先に私の面倒を見てくれる人がいればよいが,いない場合はすごく大変。私だけの問題ではない。
Mさんのボランティアさん
ボランティアの交通費の支給について,横浜市では問題が生じている。
ガイドボランティア制度の説明に行ってきた。これまでは4時間で1回1450円の報奨金がボランティアに出ていた。1450円で交通費,食事代などまかなっていた。1回8時間,1ヵ月に12回使うことができた。これまで私たちボランティアは8時間以上になってしまう場合にも対応してきた。
横浜市の制度が変わり,ボランティアの報奨金が1回4時間で500円となった。交通費込みで500円ではボランティアをするのが大変になる。500円以上交通費がかかる場合,利用者さんにお願いするのは気の毒なので,畢竟近場の方のボランティアをするようになる。
横浜市は48時間使えたボランティアのガイドサービスを30時間にする方針らしい。 これまで障害種別に異なっていた報奨金が一律500円と定額かつ低額になった。
Mさん
これまで48時間使えたガイドヘルパーさんは,30時間と少なくなった。しかし,私が相談員のボランティア,横浜市の地域ボランティアをしていることを身分証明書を添付して詳細に説明したところ,特別に加算してもらえた。
ガイドヘルパーの制限時間を決める際,横浜市は14万人いる障害を持つ人の内1万人にアンケートをとり,視覚,知的,身体障害の異なる障害を持つ人が必要とするヘルパーの平均値をとった結果と説明している。障害特性に応じた配慮をすべきなのにおかしい。
多くの障害を持つ人はボランティアどころか通院のみで精一杯という人も多い。やっと食べ物を買いに行く位の人も多い。
古野さん
横浜市の見直しは主に財政的な問題によるのでしょうね。障害者は外出するのに困難であると市が認めているのにそれを改悪しようとしているのはおかしいですね。
小野
使わない人がいるからとそれに合わせるのはおかしい。使えない理由が考慮されていない。
古野
もっと障害をもった人が積極的に外出できるようにしなければ。
Mさん
障害者をもっと引っ張り出すようにしないと。みんな使えないんじゃなくて,出ていけないでいるんですよ。みんな外出するような余裕がなく,やっと通院したり,食べ物を買ったりしている人が多いですよね。暗い顔して家の中ですわっているんですよ。
Mさんのボランティアさん
内容も余暇に使ってはいけないとか,会食につかってはいけないとか,とてもきびしいです。
Aさん
余暇につかってはいけないということがどこかに明文化されているんでしょうか。
Mさん
あるんです。
Mさんのボランティアさん
ヘルパーさんをみなさん買い物とかに使っていると思うんです。ボランティアさんと分けて内容を。
Mさん
行った先に指導者さんがいるとその時間はヘルパーさんにはついていてもらえないんです。ですからこまっちゃう。
古野さん
そういう制約は地方自治体毎に違うんですよね。
Mさんのボランティアさん
今度報奨金が500円になったところで,そこは緩和しようということです。
ええっ~
古野さん
緩和するというのは使い方は自由でいいってことですか。
Mさんのボランティアさん
みなさんのアンケートの結果でみなさんの希望を容れる代わりに報奨金については厳しくした感じですよね。
Kさん
もしご存じでしたら,障害児の通学支援について教えてください。
例えば盲聾の子だったりしたらスクールバスがあったりするでしょう。それ以外の普通の学校に行っている子などは,例えば定時制高校に行っている障害のあるお子さんなどはとても不自由しているんですけどね。通学支援はどうなんでしょうか。
古野さん
1頁に書いてありますね。障害児通学支援事業として,養護学校等の通学路に「通学支援員」を配置し,生徒の見守り,声かけを行います。とあり,これが通学支援として雇っていたんでしょうね。それを雇用ではなくボランティア制度に統合しますとありますから,ガイドボランティアに障害児通学支援事業を担わせるということでしょう。
Kさん
その子にガイドヘルプとしてつくんじゃないってことですね。
古野さん
これまで見守りしていたガイドボランティアが障害児につくということでしょうね。その代わり時間的制限があると。その制約も地方自治体で違うんでしょうね。確か。ボランティアは1回4時間で1ヵ月12回使えるということですね。12回しか学校にいかないってことはないですよね。往復使うとしたら6回ですよね。
浅野さん
そもそもですね,盲学校,聾学校,特別支援学校は,寄宿舎があるんですよ。通学は一人ではできない前提でね。遠隔地でなくても,すぐ近くに自宅があっても通えなければ寄宿舎に入るんですね。寄宿舎から学校までスクールバスが連れて行ってくれるんですね。
古野さん
それは千葉県ですか。
浅野さん
全国です。東京もありますよ。
Kさん
盲聾はあるんですけど,恐ろしく限られた場所にしかない。数が減りました。大田も品川も減りましたからね。
浅野さん
葛飾区で言えば綾瀬というところにあるんですが,盲学校はスクールバスがあるので,スクールバスが送るんですね。
Kさん
障害があっても普通学校に行ってる子もいるわけですよね。そういう場合非常に不自由しているわけです。
浅野さん
特別支援学校については問題ないってことです。
古野さん
盲聾学校に行くってことが少なくなってきていますね。
Kさん
普通本人が希望すれば別ですが,親子は一緒に暮らすというのが当然でしょう。それが盲聾であるが故に寄宿舎にはいらなければいけないというのは家族としてはつらいことですよね。本人がつらいんじゃないかと思いますよ。
浅野さん
そうじゃないと思います。普通学校の方が本人がつらいと思いますよ。学習についていくのが大変だから。黒板が見えないし,先生の声が聞こえないし。本人がついていけないんですよ。
Kさん
ついていけないって決めちゃうのではなくて,ついていける工夫をこれからしていかなくてはいけないと思うんですよ。そういう工夫も進んでいますし,逆に目の見えない先生が教壇に立っている場合もある。その人たちにどのように配慮していくか,なるべく一緒にできるように考えていかなければつらいと思いますよ。
私はある盲の方,もう今はひいおばあちゃんになっていますが,その方に言われたことがあります。昔は戦争に息子をとられたが,今度は孫を学校にとられたと泣かれましたよ。おにいちゃんは障害がないから普通学校に家から通っているけれど,下の子は聾だから,寄宿舎にはいらなければいけないと。7歳になるかならないかのお子さんが一人で寄宿舎に入らなければいけないのは家族としてはつらい。それを克服してこられた方はいらっしゃると思いますが。
古野さん
Mさんのお話をまとめると,使い方は多少緩和されるけれど時間数は減るということですね。緩和するけれど待機時間が自己負担というのは変わらないのでしょうね。
Mさん
同行援護に移行してからそうなっています。事業所もまだ同行援護になっていないところがあります。一つはなっているが,もう一つはなっていないので,私の詩吟の時に隣に座って下さる。病院も中について来て下さる。もう一つの事業所は同行援護になりましたから,入り口のところで「はい,さようなら」です。
古野さん
同行援護とガイドヘルプというのを理解していないんですが。
Mさん
今日は事業所の方が見えると聞いていますから,その違いを伺いたいと思っています。
視覚障害の方だけが同行援護という名前になったようですが,その辺よくわかりません。
小野
坂本さん説明していただけますか。
坂本さん
昨年の10月までは移動支援で地域生活支援の中で市町村事業だったんですね。市町村事業というのは市町村が主にやっている事業なんで,当たり前ですが,市町村の考え方で使い道が広かったんですよ。ところが10月からの同行援護というのは国の法律の中の制度になったので,基本的には公序良俗に反するとか,長期の学校,施設など長期のものは使えないとかがあります。国の制度ですから,各市町村に同行援護の要項がありません。国の決めたことに従ってやっているだけなので,あとは事業所の考え方だけです。一割負担については,以前からと変わらずに同行援護になったからといって個人負担が増えることはありません。前と同じで,0円負担の人が非常に多くなりましたね。18才以上で所得税を払っていない人は全員0です。所得税の額によって9000円までとか,36000円までとかという限度額はあります。それ以上使えばお金がかからないということです。お金がかかるというのはそれだけ収入があるということです。収入のない人はかかりません。ちゃんとした数字はわかりませんが,8割くらいの人には負担なしでやっています。同行援護になって市町村事業でなくなった大変さは出てくると思いますが,それは事業所でいくらでもカバーできる問題ですから。事業所の方は面倒です。請求先が国保連ですから面倒くささは出ていますが,市町村だと普段からつきあいのある地元との関係なので,それから先ほどの時間数が減ったとおっしゃっていましたが,意味はよくわかりませんが,時間数というのは国も県も制限していません。何時間使いなさいとか,何時間が限度ですよとかそういうのは国も県も言っていないんです。市町村がいっているだけです。都内で30時間というところがあるとすれば,それは区市町村が勝手に言っているだけで,50時間にすることも100時間にすることも,いくらでもできるんですよ。国はなにも言ってないんですからね。それをいかにも言っているようにしているだけです。
例えば私が住んでいる朝霞市は月128時間です。無制限に,誰が行っても128時間くれます。市役所に行くと「あなた何に使いますか,散歩ですか?では一日に1時間で30日だから30時間ですね。」と言われてしまう。そんなふうに30時間と決めてしまう市町村がほとんどですが,私に言わせれば,非常にきつい言い方ですが,そこの市町村に住んでいる人が市町村に何も働きかけていないということでしょう。市町村と話しをして,どんどん,どんどん増やしてもらえばいいと思います。これはどこに訴えても時間制限はつけていませんよ,と言われるだけです。市町村が勝手にやっているだけですから。
Mさん
私は住んでいる区にしか言えないでしょう。一生懸命言ってもみなさん48時間だから,あなただけ増やすわけにはいきません,とずーっと言われています。
坂本さん
48時間という根拠がわからないでしょう。
Mさん
根拠はわかりませんが,そんなものだろうと思っていました。小金井の人に聞いたり,千葉の人に聞いたりすると,朝5時~ゴルフについて歩いて,夕方暗くなってから帰るのも認められている,ところが私たちには認められない。ゴルフなんてとんでもないと。
坂本さん
それだけ市町村のばらつきがあるんですよ。それは市町村に対して要求をどんどん,どんどん言っていけばよいと思います。みんなで。一人だけで言ってもだめですから。
浅野さん
団結して意見をいったらいいんですよ。
坂本さん
意見を言って,市町村とどんどん話しをしていけばいいんですよ。
Aさん
それにはあらゆる市町村のデータを取って,市につきつけるくらいじゃないとだめですよね。よそではこういうふうにやっているって。
坂本さん
よそでやっているって言うのもいいかもしれないですが,基本的には国ではそういう時間制限はつくっていないということですよ。
Mさんのボランティアさん
Mさん差し置いて質問していいかしら。
時間数が増えるとヘルパー事業所に払うお金が増える訳じゃないですか。横浜市の場合はその資金がないということですから,時間制限はなくともやむを得ずということになってしまいませんか。
坂本さん
同行援護の場合の費用は国が半分,横浜市と区がさらにその半分。ですから4分の1ずつで済むわけです。ところが,市町村事業の場合には全面的に市町村がもっているわけです。
Mさんのボランティアさん
4分の1だとしてもその費用が出せないと言うことですよね。
坂本さん
ですから,それは交渉次第です。今は市町村,自治体と交渉するほかないです。だから朝霞の場合は BRAILL MEMO POCKET(ブレイル・メモ・ポケット)も日常品として認めてもらいました。これは点字の電子手帳のようなものです。点字で入力できて,MEMOができる。小さなリモコンくらいのもので,25~6万円位するのですが,どこの市町村もそうだと思いますが,盲聾者の人には支給するとなっていると思います。全国どこもだと思います。盲聾者には日常生活必要品として支給しているところがほとんどです。朝霞の場合は朧をとってもらったんです。盲ならもらえると。
浅野さん
視覚障がい者で年を取ると耳が遠くなるので,盲聾者に近い形になるので,必要ですよ。という形で。
坂本さん
私が知る限りでは3つの区がなっていると思います。それはそこに住んでいる視覚障がい者の方が働きかけないと。
古野さん
坂本さんの場合は朝霞市に団体で交渉するんでしょうか。
坂本さん
勿論。
古野さん
Mさんの場合は区に対して団体で交渉することはあったのでしょうか。
Mさん
私はもともと東京都に勤めていましたので,もっと大きな組織には入っていました。けれど,鶴見区の視覚障がい者の団体には入っていません。
Mさんのボランティアさん
会はありますが,入っている人は本当に少ないです。
坂本さん
みんなお年寄りばかりですよ。
古野さん
交渉するような団体はあるんでしょうか。
Mさん
ないですね。
Mさんのボランティアさん
そういった交渉をしたということは聞いたことがありません。そもそも発想がありません。
Aさん
今のようなそういう話しを聞く機会がないんでしょうね。
坂本さん
そういうことを言っていかないと,行政はそれでいいんだというふうに思ってしまいます。それ以上の発展がありません。そういう発想がないということは,はっきり言って,自分で自分の首を絞めているようなものですよね。私自身は同行援護になってどこが不自由になったんだろうって不思議に感じるくらいです。
ですから,先ほど言っていたような,中抜け,病院の入り口まで送って,あとは病院でお願いしますといっているわけですね。ですから,市町村に言ってみて下さい。病院のどこにそんな余っているような人がいますか。最後までついてくれるような人なんていないでしょうと。じゃあ,病院に行くときには市のケースワーカーが病院で待っているようにしてくれと,病院の中はあなたが案内しなさいと,ヘルパーさんには待ってもらいますからと。
浅野さん
病院でトイレにいくこともあるでしょう。そういうとき困りますよね。
Aさん
病院の外で待っていてもらうときの費用はどうなりますか。
坂本さん
勿論かかりますよ。費用はかかりますが,中は案内してもらえない。できない。病院の中は病院の人にやってもらいなさい,という言い方です。行政は。
Aさん
そういう法律はあるんでしょうか。
坂本さん
ないです。
Aさん
事業所毎に決めているんでしょう。
坂本さん
いや,決めてないでしょう。事業所ではそういうのは決めてないのですが,うちも事業所やっていますが,うちでは堂々と入らせてもらっています。それは市との話しで。市の方に冗談じゃない!困るのだから,入れないなら,ケースワーカーを派遣してくれと。結果,朝霞市は暗黙の了解をしています。
古野さん
文書で認めているところはすくないけれど,暗黙の了解をしているところはあるんでしょうね。
浅野さん
運用レベルです。
坂本さん
運用の問題なんですよ。運用の問題を自分たちのために良くするためには市町村と話しをしなければ。市町村の方からそういうことを言ってくることは絶対ないですから。他の市に住んでいる人間が言いにいくわけにもいかないわけですよ。もし,言ったとしたら,なんで人の区に口出しするの,ということになります。地元の人が本気になってやらなければ,市も本気ではやりません。僕が思ったのは,日盲連あたりが厚労省に話しをして,全国統一で,厚労省からの指示でできるようにするとか,ですよね。それをやるのは日盲連しかないですから。
浅野さん
実務レベルでは難しいと思いますよ。運用レベルにおとしていかないと。全然良くならないですよ。
坂本さん
日盲連が厚労省と話してくれれば,あとはおっしゃるように市町村でその市に住んでいる人が話をするしかないですね。それをしないと市町村は何の発展性もないですね。
Mさん
事業所は全部行動援護にかわったんですか?今移行の時期ですよね。2年後に事業所が全部変えたときから,その事業所のやり方が変わってくるわけでしょう。私の使っている事業所はその制度ができてすぐ行動援護に変わったの。そしたら,去年の私の行動はすべてチェックされましたよ。その事業所は詩吟をやっている間もゴルフをやっている間も全部ついてくれていたわけ。それが全部チェックされて,全部外しなさいと。
坂本さん
何で市がそこまでやれる権利があるわけですか。
Mさん
わからないですが,監査でもって引っかかったからだめですって。 詩吟の教室までチーフがついてきて,Mさんの場合には私たちで面倒見られないので,お教室の方で面倒みてください,という言い方なわけです。だけど,お教室の人達はお月謝払って自分で習いにいっているのだから,そうは頼めないですよね。それでボランティアさんたちに行っていただいているわけです。そんなことですから,全国的にどうなっていくのかわからないです。同行やっているところといないところがあるので,サポートの入り方が違っています。
坂本さん
基本的には誰のためにやっているのか,ということになります。事業所は。市町村のためにやっているわけでもないし,ただ,今の介助ありと介助なしでは,介助ありの方ばかりやっている事業所があります。これは介助ありの方が事業所の収入が多くなるから。時給が約倍くらいになりますから。介助ありになると。事業所にすれば,同じ時間やって4000円入って,1000円ヘルパーさんに渡せば,3000円の収入になる。事業所の場合介助ありしかやっていないという事業所は出てくるかと思います。そうしないとやっていけないと。介助なしだと1900円ちょっとでヘルパーさんに1000円渡すと900円しか入らない。そういうことになります。
同行援護になって全国的に大幅な変更があるように感じられますが,事業所として今までと違うところは,請求の仕方が違うのと契約をしなくちゃいけないというその2点だけで,あとは変わりません。来月の計画書を出しなさいという事業所もあるらしいですが,それは事業所が独自に求めているだけです。事業所は自分のところで作らなくてはいけないのですが,それを利用者に書かせているわけです。そうすると自分たちはそれを書かなくてすむじゃないですか。つまり仕事が一つ減るわけですよ。事業者が勝手にやっているわけですからそういう事業所とは契約しない方がいいというわけです。
Mさんのボランティアさん
横浜市が48時間という時間制約することになりそうですが,それはどういう思惑からでしょうか。
坂本さん
それは横浜市に聞いていただかないとわかりませんが。やはり,お金の問題でしょうね。
Mさんのボランティアさん
ということは,朝霞市は財政的に豊かなんでしょうか。
浅野さん
それは関係ないです。国の制度だから。
坂本さん
同行援護というのは視覚障害だけじゃないですか。知的障害だとか,精神の場合は移動支援でやっていますから,これは市町村事業のわけです。市が負担するわけです。そうすると視覚障がい者だけなんで128時間なの?知的障害者には128時間くれないの?ということになると,市としてはみんなに128時間やるしかないじゃないですか。上限を決めるというのは,これ勝手に自治体が始めていることであって,何度も言っていますが,国はひとつも時間の制限は言ってないんですよ。だからそれを根拠に直接横浜市と交渉するしかないですよ。
Aさん
同行援護もガイドヘルプも同じ立場ですか。
坂本さん
ちょっとその意味がわかりませんが。
Mさんのボランティアさん
横浜市のガイドヘルプは30時間と書いてあるんです。同行援護で実際働くのはガイドヘルパーさんですよね。ということは同じふうに考えてもいいんでしょうか。
坂本さん
同行援護をするヘルパーさんは講習を受けなくてはいけないんですよ。それだけの問題です。利用者からすれば全く関係ないですね。好きにやってもらいえばいいので。
Mさん
私なんて30時間になったら恐怖ですよ。動けなくなっちゃうから。
坂本さん
だから,直接横浜市と話しをするしかないです。それもけんか覚悟でね。
Mさんのボランティアさん
決まってないのに勝手に市が決めてしまうのは違法ではないですか。
坂本さん
それはこちらの清水弁護士と話してみてください。
小野
日盲連の代表は竹下先生ですよね。要望書を出してみるというのはどうでしょうか。
松尾さん
これは横浜市が募集していたアンケートでしょうか。
Mさんのボランティアさん
利用者の意見をということで,これに葉書がついていたんです。皆さん書いて出しました。
坂本さん
それに皆さん反対の意見を出せばいいなじゃいですか。
Mさんのボランティアさん
みんな出しているんです。
松尾さん
これは理想論かもしれないですが,どこの 市町村にいっても同一内容になる,そういう風にするにはどうやったらいいんでしょう。市町村に格差があるというのはおかしな話しでしょう。
坂本さん
一律ということになると,大概低い方に統一されてしまうので,うちなんか困りますよね。
松尾さん
あとは,当事者の方もそうですが,周りの人間,弁護士や我々のような団体を含めて,どれだけ関心を持つ人がいるかでしょうね。議員でもいいですよ。
坂本さん
そういうことですね。一番早いのは市議会の議員さんを使って福祉課と話しをしてもらうことです。ただ,話しをしてもらうにもバックがないと,支援者がないとできないですよ。やっぱり当事者ですよね。だから,国の制度でおかしいところはいくらでもあるじゃないですか。同行援護の場合も行った先で代筆,代読はできるが家の中ではできないと。でもそんなのかまわず,家の中でもやっちゃうんですよ。
浅野さん
運用ベースでやってしまえばいいんですよ。例えば,スーパー行くのでしたら,それを利用するんですよ。要は移動支援だから。でも実際にはどうなんだって話しですよ。運用ベースでカバーしていくってことですよ。
Mさんのボランティアさん
ボランティアは臨機応変にやっているんですが,時間だの回数だのと言われるとそれは壁になってしまいます。私たちからすれば突然降ってわいたように変更になるのはびっくりです。
松尾さん
この説明書によると,ボランティアをもっと増やそうっていうことですか。安いから。
Mさんのボランティアさん
そうなんです。
坂本さん
なぜ,ボランティアさんに制限時間を設けているんですか。
Mさんのボランティアさん
報奨金の関係ですね。
坂本さん
それでボランティアさんまで制限をつけているんですか。
Mさんのボランティアさん
逆にボランティアが減ってしまうんじゃないでしょうか。
坂本さん
持論ですが,行政は絶対ボランティアを使ってはいけないと思っています。みんなそのために市県民税を払っている訳じゃないですか。市役所がみなボランティアでやっていたら市県民税なんて払わなくていいじゃないですか。そうでしょう。市県民税を払う代わりに職員はプロとして仕事をしてくださいよ,ということなんですよ。中にボランティアの人がいたら税金返せ!ですよね。だから行政というのは絶対ボランティアを使ってはいけないというのが原則であって,それと,誰がやってもお金をもらえるようにしないと,資格資格というのは国がいうから仕方ないのかもしれませんが,自立支援法になって資格が必要になって24時間介助の人は非常に困っているわけですよ。なぜかというと,資格を持っている人は主婦が多いので,夜中の介助まで出来ないんですよ。それまでの支援費の時は誰でも払えたんですよ。学生の人にアルバイトで夜中見守りをお願いすることもできた。ところが,資格資格という風になってきたために夜をやってくれる人がいなくなって非常に困っている訳です。そういうところもあるんですけど。ヘルパー資格がないと,事業所は派遣できません。誰でもよかったのは支援費のときです。
Mさん
自律支援法前の支援費のときは,資格のないガイドヘルパーさんがステーションから派遣されてきていました。講習を少し受けた位で。全部ヘルパーさんとして来ていましたよ。資格はなかったけれど。今は資格がないと働けなくなってしまったけれど,私が当初使い始めたころは,「じゃあ,私登録するわ」と近所の方が手を貸すような形でヘルパーステーションに登録して来てくれました。
Aさん
今は最低2級の資格がないとヘルパーとして働けないわけですね。
Mさん
それが一つの壁になってるんですよね。
坂本さん
ということは,ヘルパー2級をもっていれば介助が上手かというと決してそういうことではなく,資格をもっていてもひどい人はたくさんいるので,そう思っていればいいです。それよりも自分の親を10年間看ていましたという人の方が上手なんですよ。ところが日本の場合は,身内の人が介助した場合はお金が出ないんですよ。ヨーロッパは出るんですけどね。そういう不備はあるんですが,あまり資格資格というのもどうかと思います。
私の事業所では講習しているんですが,利用者さんが講習を受けたガイドヘルパーさんの方が安心出来るというので。それじゃやるしかないよねということでやっています。
とにかく,運動ですよね。市町村に対する。
古野さん
Mさんには今から運動しなさい,といってもいきなりの話しで難しいと思いますが,視覚障害を持つ人の会などで,市や区に対して申し入れしよう,というのは必要だと思いますね。直接自分たちがやらなくても区議さんや市議さんがいればそういう人達のコネクションをつかってやるとかですね。福祉関係については,私は自閉症協会なんですけれども,今は東京都にあれこれ言っていっても,「それは福祉でやっているからそっちに行ってくれ」と言われてしまいます。これからは福祉は市区町村に直接下ろしたと言っていますからね。
坂本さん
確かに市町村にだいぶおりていますよね。
Mさん
法的なものは当事者に文書で何も送られて来ないですよ。
坂本さん
それはHPとか直接市町村に行って得るしかないですよね。
Mさん
包括支援センターのケースワーカーに聞いてもわからないということでした。
坂本さん
基本的に包括支援センターは介護保険の方ですから,障害のほうはわかりません。
Mさん
区に聞いても,前と何もかわらないから,同じように利用していいですよ,というだけなんです。名前が変わっただけで,と。
坂本さん
そうですか。じゃなくて,資料を下さいと言わなければ。ただ,同行援護については資料を作っている市町村は少ないです。国の制度なので,市町村で作らなくてもいいということです。国の方を基準としているんで。
Mさん
でも手元にはあるんじゃないですか。
坂本さん
それはあります。国は都道府県の課長を集めて課長会議で説明していますから,勿論市町村にはおりていきます。それは資料をくれるはずです。ないわけありません。
Mさん
ではもらわなくちゃ。
古野さん
横浜市障害福祉課事業者担当説明会資料で,点字版,録音版もあると書いてありますよ。
横浜市はあんしん福祉財団とかありますよね。福祉には力を入れていると。
坂本さん
以前は住むなら神奈川県にと言われていましたよね。
Kさん
子供の教育についても神奈川がいいと言われていましたよね。
坂本さん
横浜市は就労でありますよね,福祉的就労,神奈川県の場合,作業所で月3000円とか,5000円でやっているじゃないですか。それを福祉的就労と言っていますよね。それを神奈川では一般企業の中で介助者をつけて普通のお金をもらって働くのが福祉的就労と言っています。普通の企業で,例えば私は目が悪いので,見える人をつけてくれて就労するのが福祉的就労であって,作業所へいっているのは就労ではなくて施設です。というくらい神奈川県はすすんでいるはずです。いざ視力障害者のことになるとだめなんでしょうか。一番はじめに就労支援センターをつくったのは川崎ですよね。電機労連がつくったのが最初です。日本で。それからあちこちに出来てきたんですから。その位,神奈川,町田はよかったです。東京よりは良かったですよ。
古野さん
利用時間の制限があるか,という点では,48時間を基準時間としますとあります。
Mさん
ボランティアさんの方はね。
古野さん
同行援護のサービス説明会の話しですよ。それと基準時間月30時間というのは平均の時間であって,横浜市がもっと増やしてもいいという話しですよね。
浅野さん
横浜市が出した基準であって,当事者と合意した時間ではない。合意した話しではないですよね。
Mさん
まだまだこれから検討していくということですね。
坂本さん
同行援護はもう始まっているんですよ。
Mさん
はじまっているところと,そうでないところがあるんですよ。事業所によって。まだ移行時期だから。10月からもう一つの事業所も同行援護にかわるので,危惧しています。
坂本さん
横浜市は同行援護の人をどんどん増やしているんだと思います。事業所も同行援護をしないと利用者がいなくなる。
古野さん
不備な点は運用の問題だから,交渉次第ということになるわけですね。
坂本さん
それがおかしいですね。なぜそんなに変わるんだろうと。うちの事業所の場合,ほとんど変わってないですよ。今までと。
古野さん
国の事業になったからには,財政的には市としては楽になったはずですよね。それを減らす理由はあまりないわけですよね。市の費用は4分の1になっているわけですから。利用者がもっとどんどん言っていけばいいということでしょう。
坂本さん
横浜市の場合おもしろいんですよ。障害者が自分で通勤しなさい,仕事も一人でやりなさい,ということを言うわけですね。その運動で市役所前でビラをまいているときに市長が車で登庁したわけですよ。市長に対して,「市長はなぜ車で来るんですか。私たちには自分で通勤しろと言っているのに,市長はなぜ車で来るんですか」と市長をかなり追い詰めたことがありました。
Mさん
横浜市の場合はグループホームをたくさん作って,自立を促すためにグループホームにでました。五年前,6年前?発達障害の制度ができましたね。発達障害の方たちも障害者手帳をもらえるようになって,就労支援を受けるようになって,グループホームから働きに出ることが増えてきたわけです。親の元にいた人たちがだいぶ外に出て,グループホームから作業所や企業に働きに出るようになった。それまでは親の負担が多かったわけですよね。親の収入によって負担額が違っていた。
坂本さん
今は18才以上になると同居でも親の負担金はなくなっています。
古野さん
Mさんの問題はだいぶ出てきたので,O君の話にうつります。ご本人のまとめの文章があります。ガイドヘルパーをつかうことになった理由と,ガイドヘルパーの利用をやめた理由が書いてあります。それはそれとして読んでください。ヘルパーさんがあれこれ指示するようになったので,それはやめてほしい,というので,利用自体をやめたとのことです。
小野
屋久島の平田さんから,源君の報告をそのまま区の福祉課に持って行ったらどうか,とアドバイスいただきました。
浅野
事業所を変えたらどうでしょう。
古野さん
浅野さんにせっかくお願いしてあるので,浅野さんにお話していただきましょう。
浅野さん
千葉県松戸市で身体障害者相談員として相談を受けています。障害のある人もない人も共に住みやすい千葉県づくり条例の相談員もやっています。その関係もあって松戸市の障害福祉課長とは結構やりとりしています。それは視覚障がい者の代表の立場でもありましたし,現在も相談員をやっています。視覚障がい者の要望事項は私を通す形で障害福祉課長に話しを持って行っています。そのために来週火曜日にあるのですが,4年に1度松戸市障害者福祉計画が策定されます。その次期の障がい者計画の策定をするための会議があります。その中にこういったものを入れたらよいとアドバイスしています。今回私が提案した中には視覚障害とはまた違うのですが,原因が分からない病気,治療方法が確立されていない病気が何千種類もあります。そういう病気を抱えたときに,私の場合は先天性の視覚障害ということでうまく対応できましたが,身体障害にも,難病にも入らない人がいても障害手帳が交付されないために福祉的支援を受けられない人が全国にはたくさんいます。地元でそういう人がいたとき,どういう対応をとるか,行政としてきちんと決めておかないといけない,検討しておかなければいけないと思います。たとえば,実際の話ですが,慢性の疲労性症候群という,一見して疲れたという症状を持つ病気があります。そういう人は疲れがひどくて,座っていることもできないんです。ご飯を食べるときも横になったまま食べているんです。そんな生活をしているのに,介護保険も障害者手帳も,障害者支援も受けられないんです。かつ,難病の指定も一切受けられないのです。そういった例があって困っているというので,私の出身は岐阜県ですが,岐阜県でそういった問題があって,多くの人がそういった状況を放置しておくのはおかしいのではないかということで,岐阜県庁に陳情しました。その陳情にもとづいて県庁が障害者手帳を交付しました。というように,運用ベースで手帳を交付するような形で支援するというように,ガイドも派遣を受けられるので,生活がきちんとできる話しになってきたわけです。そういうことで予め事例を考慮して計画をたてなければいけないということで,今取り組んでいる最中です。
古野さん
それは障害者福祉計画ですかね。2年に1度作成する計画に盛り込んでほしいという要望をしているわけですね。
浅野さん
松戸市は48万人もいますが,身体障害者手帳は県が交付しているわけです。ところが,隣の柏市は35万人の都市ですが,中核都市として認められているので,中核都市は市が独自で身体障害者手帳を交付することが出来るわけです。それは横浜市と一緒ですよ。そのために今現在,難病などで,手帳を受けられない人がいた場合,隣の柏市にでも引っ越してきてもらって,柏市に交渉して手帳を受けた方がいいんじゃないか,ということを私はアドバイスしますよ。でも,それじゃあおかしいですよ。自分の住んでいるところで手帳をうけることができればある程度根本的な問題は緩和できると思います。ということを話し合いしていますが,なかなか難しいです。私自身市に週に3日通ってロビー活動もしてきましたし,議員さんにも視覚障がい者に関することで視覚障がい者協会というのがありますが,そちらの方でも真摯に取り扱ってほしいということで働きかけをしています。そういった活動をしています。
松尾さん
松戸はそういうふうに真剣にやってくれますが,他の市ではないと思いますよ。
浅野さん
ないと思いますよ。私自身がたまたま関わったことで,自身が知っていますから,TBSの系列のテレビ局でも放映されました。
Mさん
情報が大事ですね。いろんな情報が。
古野さん
松戸市は,あえて今中核政令都市になろうとはしていないわけですね。
浅野さん
その意向はないです。かといって,合併する予定もないんです。市の運営上の話しで,市長の考え方は,3年前までは2週間に1度くらいあっていましたから,ツーカーの中だったんですが,市長がかわってしまったので,断ち切れてしまいました。今の市長は何考えているのか分からないですね。
古野さん
今の市長は難病というか,障害と認定されていない人たちの救済をやろうかと言っても市長が言うこと聞かないわけですね。福祉課位が話しを聞いてくれるということになりますか。
松尾さん
松戸市のガイドヘルプサービスはどうですか。
浅野さん
去年の9月までは30時間でした。月に。ベースはね。今は同行援護が始まっているので,現在は特に制限はなく,初めての人には50時間というトライアルをベースとして持っています。
古野さん
時間数はよくなったということですね。
浅野さん
横浜市の資料の利用時間の,宿泊を伴う外出について ホテルなどに宿泊したときに使えるか,ということですが,運用ベースで実際には使えます。同行援護の可能なガイドヘルプサービスに完全に移行していないので,そういう意味では全員が全員できるかというとそういうわけではないんですね。いずれは一泊宿泊付の外出も可能になってくると言うことなんです。
古野さん
武蔵野市はどうなっているかわからないですが,旅行はだめということになっていたのですが,連続して使うということにしたらいいのではないか,というようなことになっていたと思います。夜まで使ったのだけれど,翌朝早くから使ったということにしたらよいというようなことです。
Mさん
同行援護になったら一泊まではいいみたいなことでした。寝ている間は抜けるみたいですけど。
それから,私は今度屋久島に行きます。平田さんにお会いしてきます。屋久島では屋久島の事業所に時間数を登録するんです。屋久島で向こうのガイドさんにお願いして行動してみようと思います。
坂本さん
そこが同行援護のいいところなんです。
Mさん
実際に私が使ってみようと思います。相談を受けている人がいて,その人は障害をもっているのですが,お母さんが田舎で一人で暮らしていて,その人も田舎で事業所を探して登録してみて,と今アドバイスしてるんです。その前に私が屋久島にいってきますから。
古野さん
では行った後で話しをきかせてください。
松尾さん
本人負担というのは,収入によって違いますか。
Mさん
同行援護は負担額は同じです。同じ条件です。屋久島で使う分こちらの事業所の時間数を減らすんです。おかむらひまわりのお家というところに登録するんです。そうやってみんなあちこちで使えるようにするといいですね。
坂本さん
その場合,注意しなければいけないのは,契約を破棄するようにしておかないと,住んでいるところでの持ち時間がなくなってしまいますから。もともとの上限監理をする事業所に戻す必要があります。
古野さん
事業所を実際にやっておられるので,アドバスがありましたら,お願いします。
坂本さん
どこでもそうなんですが,自分の住んでいる自治体への訴えが視覚障害の場合非常に少ないように思います。それだけ視覚障害者は恵まれているんじゃないかと思います。問題があったら訴えていくと思いますから。128時間朝霞市で出ているのもみんなで使って,朝霞市からするとこれだけ必要だとうことを分かってもらったということです。役所は必要だからくれるということですから。自分たちでどんどん動いていくことが必要だと思います。
丸田弁護士
勝ち取るということですね。
Aさん
それと,一人じゃだめですよね。やはり人数が集まらないと。
浅野さん
それから,自分の権利を勝ち取るための勉強をしなくてはいけないということです。努力をしなければいけないということです。
坂本さん
それから,行政の仕組みをよく知って,情報を取るということですよね。
浅野さん
障害福祉課の窓口に,障害の専門家を配置するように要望しているんです。
松尾さん
行政とはお互いに顔見知りになっておくことですよね。情報交換できるようになっていることが必要ですよね。
坂本さん
私が言う運動しなさい,ということは喧嘩しなさいということばかりでなく,仲良くしなさい,ということでもあるわけです。行政とうまく関係を持たないと。
古野さん
障害者の歴史を見ても,声が大きい方が勝ち取っているということでしょうね。
坂本さん
朝霞の駅前はすべて音声が出るようになっています。朝霞に来てみて下さい。何もなければ,バス停はただ黙って立っているだけですから。
古野さん
同行援護の話しはこれで終わります。