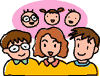1.大阪発
知的障がいのある男性の建造物放火事件
異例の公訴取り下げ 担当弁護人の話を聞く
弁護士 荒 井 俊 英 氏
2.障がい差別の現状と何を改革すべきか差別事例だけでなく、好事例の紹介も含め
日時:2011年1月22日(土) 午後1時30分~
場所:戸山サンライズ
今回は知的障がいを持つ人の弁護人の荒井俊英弁護士のお話と障害者差別のない事例報告と二段構えの学習会をもつことになりました。お正月気分の抜けない1月ですが、貴重なお話が伺える機会を得ました。
22年11月大阪地検が現住建造物等放火罪で起訴された知的障害をもつ男性の公訴を取り下げました。地検が控訴を取り下げるのはごくごく異例なことだといいます。大阪地検については厚生労働省の村木さんの事件が記憶に新しいだけに、また大阪地検か、と更なる驚きをもって報道されました。人権ネットワークの事務局をおく銀座通り法律事務所在籍荒井俊英弁護士が弁護人を務めていた事件であることから、今回、お話を伺うことにしました。この男性は取り調べ中「事件当日は自宅で寝ていた」と供述、その後「うそをついた」と翻すのですが、この経緯が検事の指示で警察官の報告書から削除されていました。知的障害のある人の証言や証拠の保存などについて問題点を含め、お話いただきます。
また、昨年の運営委員会で、いつも障害者差別のみを話し合う学習会をしているので、障がいをもつ人の生活、学校生活、就労がうまくいっている事例について報告しあう会ももちたいということになりました。報告事例をお寄せください。勿論、改善を望む事例の発表でもかまいません。
学習会報告
大阪発 知的障がいのある男性の建造物放火事件
異例の公訴取り下げ 担当弁護人の話を聞く (弁護士 荒井 俊英 氏 )
取り調べの可視化が大きくクローズアップされた正にその時に、学習会の講師として、当該事件の弁護人を務められた荒井先生にお話を伺う機会が得られました。一方的に聞くだけの学習会ではなく、それぞれが思ったこと、制度についての質問などを交えて学習会がすすめられました。
弁護士さんや修習生の方など多数の法律関係者の参加をいただきました。
参加者の掲載可とお書きいただいた方の感想をお伝えします。
ざっくばらんに話していただき、分かり易く理解できるところが多い。講師は最初はかたい幹事の話し方のように見えたが、時間がたつにつれリラックスしてきて、話し方もなめらかになり、前半より後半の話が親しみが持てた。
被害者が二次被害にあっていることを話していたが、やっぱりな~と思った。二次被害については、おおよそ想像ができた。講師は二次被害を新聞に載せて欲しいと言ったが、載せなかったことにがっかりしていたようであるが、とにかく言ってみることが大切。期待どおりいかなくても、まずは言ってみること。新聞社は営利企業であるので、利益になることは載せ、ならないことは後回しか不問だが、それでも新聞社、記者にアプローチすることは大切である。
司会者のはなす時間が多く、むしろほとんどしゃべらない参加者に自分の気持ちを発表できるように考え、参加者が話をするのがよいと思う。 (Kさん)
検察官といかに攻防したか、細かいところまでお話いただき、貴重な体験になりました。
障がい者の方の「弱さ」につけこむ検察官の姿勢は想像以上のものがあり、恐怖を覚えます。
将来弁護士としてどのように闘えばよいか、参考になりました。(Sさん)
刑事裁判を闘って行く上で、「通知書」や「申入書」等の事実上の書面による取調べの適正確保が重要なんだと知りました。また、内容証明郵便による書面作成も、検察に対する対応と警察に対する対応では全くの手の内を見せる度合いを異にする等、弁護士手法にも工夫が必要だと理解しました。
知的障がい者が被疑者になる刑事事件においては、捜査機関のみならず弁護側含めて法曹三者の知的障害についての専門的理解が必要であり、この理解なくして知的障がい者の人権擁護は不可能だと思いました。(Nさん)
色々なキャリアの法律家の現場の声(参加者も交えて)と専門家でない市民の声が混じって、メディアで目にすることがない話を聞くことができる貴重な機会でした。(法律に詳しくない方には所々難しいのでは?という語句があったのですが、大丈夫だったのか少し気になりました。)
犯罪等に巻き込まれるという、健常者でも「非日常」なことと、社会の一員として活動するという「日常」との両面で、今よりできることは多いと思います。まず目を向けるところから、と初歩的なことですが、改めて意識することができました。(Yさん)